FCバルセロナは、財政と戦術という二重のプレッシャーの中で2025年夏を迎えている。
最大の課題は、ラ・リーガとUEFAが課す厳格なFFP(ファイナンシャル・フェアプレー)規則。
そしてもうひとつが、ハンス・フリック新監督の下で進む戦術的再構築。
クラブは「1対1ルール」への回帰を目指し、アンス・ファティやラングレら高額年俸選手の放出を進めつつ、バルサ・ビジョンのレバー資金回収や債券発行による資金調達など、あらゆる手を尽くして財政再建を図っている。
一方フリック監督は、厳格な規律とインテンシティを武器にしたゲーゲンプレッシング型サッカーを浸透させるべく、限られた戦力の中でのチームビルディングを進行中。若手の抜擢と既存戦力の再評価によって、「ポゼッションからの脱却」を模索している。
借金、債券、若手起用──制約下のチーム再建は、希望とリスクの両面を孕むプロジェクトとなる。
今回は、そんな2025年夏のバルセロナを形づくる「財政と戦術」のリアルに迫る。
FFP問題と「1対1ルール」復帰への道
FCバルセロナにとって、今夏の移籍市場最大の障壁は、ラ・リーガが定める厳格なサラリーキャップ規則(LCPD)──通称ファイナンシャル・フェアプレー(FFP)だ。
数年前からバルサは「1対4ルール」という不利な条件下に置かれており、選手1人の放出で浮いた給与の25%しか新たな登録に使えない**状態が続いてきた。
しかし2025年夏、クラブは念願の「1対1ルール」復帰を目指しており、これは放出と同等額の登録が可能となる最も有利な状況だ。この回復のために、バルサは3つの施策を並行して進めている。
FFPの基本とバルサの現状
ラ・リーガが導入しているLCPD(Limite de Coste de Plantilla Deportiva)は、クラブが支払える選手人件費やスタッフ報酬の上限を決める制度です。これはクラブの収入・支出のバランスを基に個別に設定されており、給与・移籍金・手数料なども含まれます。
バルセロナは、これまでの数年間で発生した巨額の赤字・レバースによる将来収入の先取りなどの影響により、リーガから「1対1ルール」ではなく、「1対4」や「1対2」ルールを適用されてきました。
「1対4ルール」:1ユーロの新規登録(補強)を行うには、既存選手の給与削減や移籍などで4ユーロ分の人件
費削減が必要。極めて厳しい。
「1対2ルール」:2ユーロの削減で1ユーロの新規登録が可能。条件が多少緩和されるが、依然として厳しい。
「1対1ルール」:1ユーロ削減=1ユーロ補強が可能となる。補強・延長契約・登録すべてが柔軟に行える。
2025年5月、ジョアン・ラポルタ会長は記者会見で次のように述べています:
また、ラ・リーガのテバス会長も「バルサが1対1に戻るには給与総額のさらなる削減と収益の安定がカギ」と明言。つまり、高額サラリー選手の放出や新収入源の確保が、1対1ルールの実現には不可欠です。
高給選手の放出と新たな「レバー」
バルセロナが「1対1ルール」に復帰し、戦力補強の自由度を高めるために避けて通れないのが、高給選手の放出と新たな収益確保(=“レバー”の発動)だ。
アンス・ファティ、ラングレらの放出予定
まず最も即効性のあるFFP対策は、高額サラリーを抱える選手の放出だ。
Barça Vision・VIP席売却など資産売却の進展
2022〜2023年にかけてクラブが行ってきた「経済的レバー」は、資産売却による資金確保という戦略だ。
最近では以下の進展が見られる:
Espai Barça後の収益計画
スタジアムの大改修プロジェクト「Espai Barça」は、短期的には多額の支出(総額約14億5000万ユーロ)を生むが、中長期的にはクラブの財政回復の要となる見通しだ。
UEFAからの制裁リスク
UEFAからの制裁リスク──水増し収入が呼ぶもう一つの試練
いくらラ・リーガの「1対1ルール」に戻れたとしても、それだけでは安心できない。
次に待ち構えているのがUEFAの監視の目だ。
実はここ最近、UEFAからはバルセロナの営業収入に対して“水増しの疑い”が指摘されている。
具体的には、クラブが行ったデジタル資産の売却やマーケティング契約の一部が、実態に見合っていないとされており、これがFFP違反につながる可能性があると報道されているんだ。
仮にこの調査で問題ありと判断された場合、
ここで押さえておきたいのは、ラ・リーガとUEFAのFFPは別物だという点。
・ラ・リーガは「予算超過=選手登録制限(1:1, 1:2, 1:4ルール)」という形で年単位で調整が入る。
・一方UEFAは、「実際の損益3年分」を軸に制裁を判断し、制裁が下れば数年単位の大会出場停止すらあり得る。
つまり、たとえラ・リーガ内で健全化が進んでも、UEFAに“過去の帳簿”を掘られれば痛手を負う可能性が残っているのが現実で安心してはいられない…
どんなクラブも、どんな企業も、過去のツケからは逃れられない。
バルサが真に健全な経営体質を取り戻すには、まだもう少し時間がかかりそうだ。
フリック監督のプレシーズン再建計画
新たに就任したハンス・フリック監督が、まず着手しているのがチーム全体への戦術意識と規律の再構築だ。
その中心にあるのが、彼の代名詞ともいえる「ゲーゲンプレス」=即時奪回型のプレッシングサッカーである。
フリックの戦術と規律の浸透
プレッシングと縦への推進力を重視する攻撃スタイル
シャビ体制下のバルセロナは、かつての伝統を踏襲する形でポゼッション重視のビルドアップに力を入れてきた。
だがフリックは明確にスタンスを変え、ボールロスト直後の即時奪回(ゲーゲンプレス)と、奪った後の縦への速い展開を軸に据えている。
特に、中盤から前線にかけてのプレッシャー強度が重視されており、既存の選手たちも「走ること」や「強度」に適応できるかが評価基準となりそうだ。
「練習1時間前集合」──規律重視のドイツ流メソッド
フリック監督の特徴は、戦術面だけでなく規律とプロフェッショナリズムの徹底にもある。
就任直後の指示の中でも特に話題になったのが、「練習の1時間前には集合するように」というルール。
これまでの“緩さ”とは一線を画す姿勢に、選手たちの間でも緊張感が走っている。
時間厳守・姿勢・食事管理──あらゆる面で「プロフェッショナルであること」が求められる環境に、チーム全体の空気感も少しずつ変わり始めている。
ペップがバルサの監督になった時も緩んでいた規律をかなり締め直したのが記憶にあります。
記憶にあるのが遅刻に関しては罰金を設けるなどでした
その後は選手の発言が強くなってしまいよからぬ噂がたくさんありましたね…
シャビとの違い、ゲーゲンプレス導入による方向転換
バルサの伝統であるポゼッション+位置的優位を重視してきたシャビとは異なり、フリックはボールより“スペース”を重視する戦術家だ。
・ボール保持ではなく、「奪ってすぐ縦に出す」直線的なアプローチ
・1対1での強さ、切り替えの速さ、連動したプレスで試合を支配する
・中盤の強度と前線の走力が命
こうしたスタイルは、ブンデスリーガやドイツ代表で培ってきたものであり、現代フットボールに適応した新しい“バルサ像”の構築を目指している。
若手の評価とトップチーム入りの可能性
ハンス・フリック監督の再建プロジェクトにおいて、若手の抜擢と評価は重要な柱の一つだ。
これは戦術的な理由だけでなく、FFP対策とも密接に結びついた現実的な選択でもある。
フアン・ヘルナンデスにかかる期待
今プレシーズンで特に注目されているのが、先日もお伝えしたフアン・ヘルナンデスら、ラ・マシア出身のタレントたちだ。
フリックは就任会見でも「年齢ではなく、プレーの“質”を見る」と明言しており、年功序列や契約状況よりも、今この瞬間にピッチで何ができるかを重視している。
プレシーズンでのトレーニングや親善試合は、彼らにとってトップチーム昇格への大きなチャンスなのは間違いない。なんとかシーズン序盤からトップチーム帯同を獲得して経験を積んでくれれば最高だ。
“ID重視”から“質重視”へ──バルサの選考基準が変わる
これまでのバルサでは、選手の“バルサDNA”や戦術理解度(ID)を重視してきたが、フリック体制では明らかに選考基準が変化している。
・技術だけでなく、フィジカル・インテンシティ・1対1での勝負強さ
・試合を変えるインパクトを持てるかどうか
・ポジションにとらわれない「スペース管理能力」への適応
こうした“質”の追求は、ゲーゲンプレスを軸にする現代型サッカーに不可欠な要素でもある。
若手起用=FFP対策という現実的選択
もう一つ見逃せないのが、若手を積極的に使うこと自体が財政面での戦略になっている点だ。
つまり、若手の抜擢は“理想”ではなく“現実”──
今のバルサにとって、最も理にかなったチーム強化策の一つと言えるだろう。
残留・放出の見極め
フリック体制の始動にあたり、クラブ内で最もシビアに行われているのが**「既存戦力の棚卸し」だ。
誰をチームに残し、誰を手放すのか
その判断は戦術的なフィット**だけでなく、年俸や契約年数といった財務的な側面も含めた総合的なものとなる。
クリステンセンの去就──「1300万ユーロ問題」の行方
中でも議論を呼んでいるのが、アンドレアス・クリステンセンの処遇だ。
昨季、シャビの下でアンカーとして起用され一定の成果を上げたものの、本来のポジションはセンターバック。
フリックのスタイルでは、より前に出られるCB、スピードと対人守備に優れたCBが求められる傾向にある。
クリステンセンの年俸はおよそ1300万ユーロともされており、この数字が残留か放出かの分岐点となっている。
しかも彼はフリー移籍で加入したため、仮に売却となれば帳簿上“全額利益”として計上できる。
つまり、FFP対策としては非常に“効率の良い放出候補”なのだ。
現在の移籍候補としては、ACミラン、ユベントス、ニューキャッスルが挙げられています。
市場価値としては1200万ユーロ(日本円で日本円で約20~21億円)だが、バルセロナは2000万ユーロ(日本円で約34億円)であれば売却を検討するとの報道もあります。
パフォーマンス次第で“再評価”も?
とはいえ、フリック監督が全てを「数字」で決めるわけではない。
プレシーズンでのパフォーマンスや、戦術理解・適応力次第では一度“構想外”とされた選手が再評価される可能性もある。
クリステンセンに限らず、今季のポジション争いは、誰にとっても「白紙」からのスタートになる。
特に、評価を上げているフェラン・トーレスや、昨シーズン終盤で右SBとして成長を遂げたエリック・ガルシアといった選手たちも、フリックの戦術にフィットできるかどうかは未知数だ。
すべては、プレシーズンのトレーニングと実戦でのパフォーマンス次第。
この夏は、バルサの未来を左右する選手選考が水面下で進む、真のサバイバルの舞台なのだ。
何はともあれ、選手間の競争が激化することは、チーム全体の力を底上げしてくれる
ファンとしては嬉しい悩みだ。
シーズンは長い。誰だって調子を落とす時期があり、累積警告やケガで出場できないこともある。
だからこそ、さまざまな局面で頼れる“フィットした選手”が揃っていることは、本当に心強い。
そして、それがもしカンテラ(ラ・マシア)出身の選手であれば、なおさら胸が熱くなる。
これからも頼むよ、Visca el Barça!Vamos Blaugrana!!



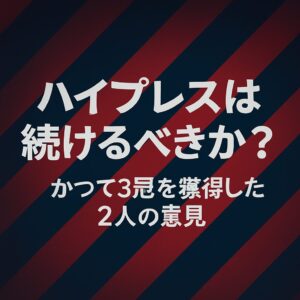

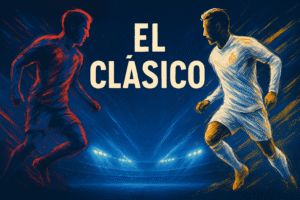





コメント